2026年労働基準法が約40年ぶりに大改正?制度変更の背景と企業が取るべき対応とは
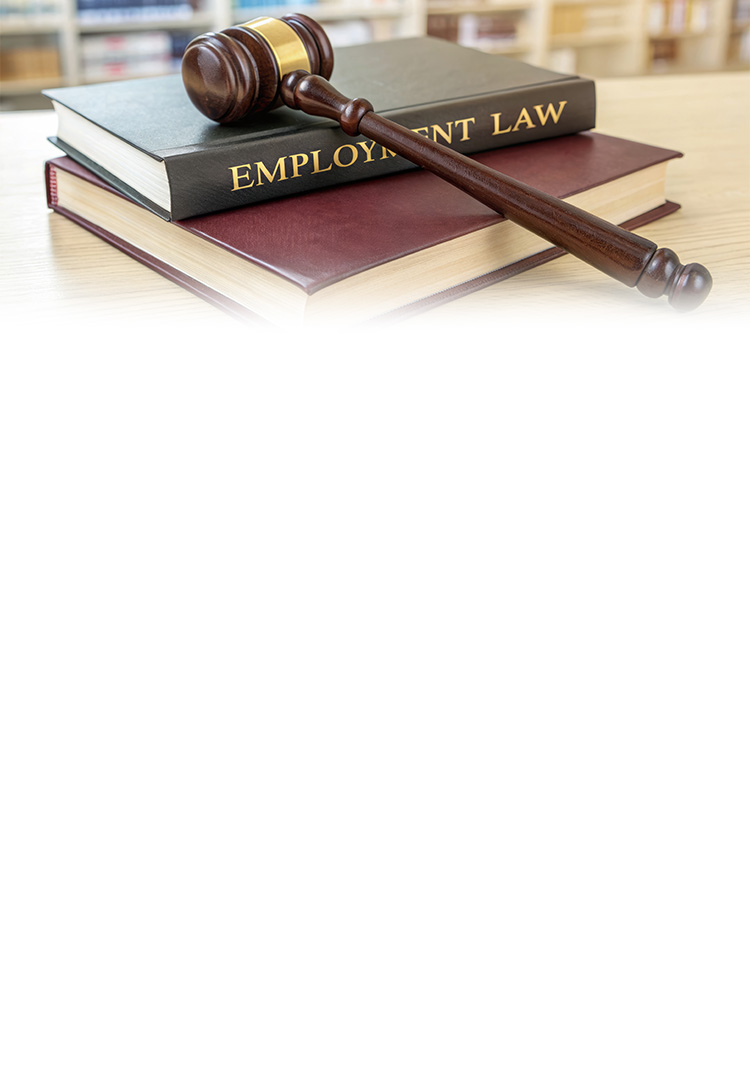
2026年、労働基準法が約40年ぶりに大改正されると注目を集めています。人事労務担当者においては法改正のキャッチアップが難しく、法令遵守リスクや業務負担の増加を懸念されている方も多いことでしょう。
2025年8月現在はまだ議論の最中ですが、改正案を示した報告書が公開されていることから、今からでも企業の準備対応は可能です。そこで本記事では、制度変更の背景と企業が影響を受けるポイント、その準備対応について解説します。
公開日:2025年9月17日
目次
- なぜ今、労働基準法の大幅改正が検討されているのか?
-
改正が実現するとどうなる?企業が影響を受ける主な項目
- 1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)
- 2. 法定休日の明確な特定義務
- 3. 勤務間インターバル制度の義務化
- 4. 有給休暇の賃金算定における通常賃金方式の原則化
- 5. つながらない権利に関するガイドラインの策定
- 6. 副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し
- 7. 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
-
どんな実務対応が必要になるのか?見落としがちな観点を整理
- 就業規則や雇用契約書の見直しが必要になる可能性
- 勤怠・給与システム改修の検討も必要
- 従業員説明・教育体制の整備が求められる
- グループ会社への展開やルール統一も重要な論点に
- 実務対応に漏れがないか確認しよう|改正対応チェックリスト(無料DL可)
-
“全部自社で対応できるか”を判断するために知っておくべきこと
- 内製対応のメリットとその限界
- 外注=丸投げではない。「一部委託でリスクを避ける」という選択肢も
- まとめ|法改正は“コスト”ではなく“リスク対応と信頼構築”の好機
なぜ今、労働基準法の大幅改正が検討されているのか?

デジタルデバイスの発展やコロナ禍を通じて、企業の環境や従業員の働き方は急速に変化しています。特にコロナ禍以降、テレワークの推進やDX化に取り組んできた企業は多いのではないでしょうか。
こうした背景を踏まえ、厚生労働省は単なる労働基準法(以下、労基法)の解釈変更ではなく、法律そのものの整備が必要と認識し、2024年1月に有識者で構成された「労働基準関係法制研究会」を開催。2025年1月に同研究会による労基法の改正案をまとめた報告書を公開しています。
報告書では、労働時間制度・休日制度のみならず、「労働者性」「事業概念」「労使コミュニケーション」の在り方といった総論的論点についても言及されたことから、法適用の在り方の抜本的な見直しが指摘されています。これに伴い企業が対応すべき範囲も広がり、40年に1度の大改正と注目を集めているのです。
なお現在(2025年秋時点)、法案そのものは成立しておらず、労働政策審議会・労働条件分科会での審議が続いています。
改正が実現するとどうなる?企業が影響を受ける主な項目
今回の労基法改正で企業が影響を受けるのは、主に以下の7項目です。
-
連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)
-
法定休日の明確な特定義務
-
勤務間インターバル制度の義務化(原則11時間)
-
有給休暇時の賃金算定における通常賃金方式の原則化ルールの明確化
-
つながらない権利に関するガイドラインの策定
-
副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し
-
法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)
定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合により困難と判断した場合には、「4週間を通じて4日の休日を付与」すれば、週休1日制の適用を受けない特例が認められています。
この4週4休の特例は、「ある特定の4週間に4日の休日を設ければよい」とするもので、どの4週間を区切っても4日の休日を設けなければならないというものでありません。そのため、理論上では長期の連続勤務が可能になってしまう点が問題視されています。
極端な例ではありますが、現行では下の図のように、4週間(28日間)のうち第1週の最初に4日間の休日を設定した場合、残りの24日は連続勤務が可能になります。さらに8週間で見た場合、第1週の最初に4日間、第8週の最後に4日間の休日を設ければ、連続48日勤務が可能になってしまいます。

いずれも4週間を通じて4日の休日があるため法令違反ではありません。しかし、精神障害の労災認定では「14日以上の連続勤務」は心理的負荷の判断基準に該当するとされ、健康管理のうえでは非常にリスクの高い状況と判断できます。
このことから今回の報告書では、変形週休制の特例を2週2日に変更し、連続勤務の上限を13日までとする趣旨の提言がなされています。
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | 特例として4週4日の変形週休制が認められている |
|---|---|
| 問題点 | 4週4日の変形週休制の場合、最長48日間の連続勤務が可能になり、連続勤務による健康上のリスクが懸念 |
| 改正案 | 特例を2週2日の変形週休制に見直し→連続14日以上の勤務禁止 |
2. 法定休日の明確な特定義務
法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであるという考えに基づき、法定休日の特定義務も検討されています。
先述のとおり、現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。
また、多くの企業が週休2日制を採用している現状から、法定休日と法定外休日の区別が曖昧な点も懸念点のひとつです。休日労働した場合の割増賃金の取り扱いは法定休日と法定外休日とで異なるため、法定休日が特定されていない場合、割増賃金の支払いに関して企業側と労働者側とでトラブルが生じる可能性があります。
法定休日にまつわる法律規律を明確にし、労働者の権利を守り、かつ企業の法律上のリスクを回避するのが、法定休日の特定に関する提言です。
もっとも、シフト勤務や1か月単位の変形労働時間制を採用する事業所では、勤務パターンごとに休日を明確に特定することが難しいという実態もあります。報告書では、こうした現場の運用実態を踏まえつつ、「柔軟性を確保しながら法定休日を明示する」ための設計指針を整備する必要があるとの意見が示されています。
具体的には、勤務表やシフト表によって休日を事前に特定する方法や、就業規則上で「休日の基本パターン」を明示したうえで例外運用を認める方式などが検討対象とされています。
一方で、休日の特定義務が強化されれば、休日労働の割増率や代休運用をめぐるトラブル防止につながる効果も期待されており、企業には自社の勤務制度と照らした制度設計の見直しが求められます。
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | 法定休日を特定する義務はない |
|---|---|
| 問題点 | 労働の健康と私生活のリズムを保ちにくい 休日労働が発生した場合の割増賃金の算定が困難/シフト勤務・変形労働制を採用する事業所では休日の特定が難しい |
| 改正案 | 法定休日の事前の特定を義務化し、勤務形態に応じた柔軟な特定ルールを設計する |
3. 勤務間インターバル制度の義務化
勤務間インターバル制度の導入を義務化するとともに、インターバル時間を原則11時間とすることが検討されています。勤務間インターバル制度は2019年4月に導入されました。しかし、努力義務であったことも影響して、直近2024年の導入実績はわずか5.7%、導入を予定あるいは検討している企業は15.6%にとどまっています。そのため、制度の詳細を知らない人事労務担当者も少なくないかもしれません。
勤務間インターバル制度は、労働者が適切な生活時間や睡眠時間を確保することを目的に、労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)の改正に伴い制定されました。
具体的には、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保するというもの。残業などによって11時間のインターバルを確保できない場合は、始業時間を繰り下げる対応が推奨されています。

このインターバル制度の定着を目指し、今回の報告書では制度の義務化を提言するとともに、インターバル時間を原則11時間とすることが示されています。なお、11時間という単位は、ヨーロッパを中心とした諸外国のインターバル時間が踏襲されています。
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | 勤務間インターバル制度は努力義務 |
|---|---|
| 問題点 | 勤務間インターバル制度の普及が進まず、労働者の健康および福祉が確保されない |
| 改正案 | 原則として、勤務間インターバル制度の義務化 インターバル時間は11時間とする |
4. 有給休暇の賃金算定における通常賃金方式の原則化
年次有給休暇取得時の賃金算定の方式を、原則として「通常賃金方式」を採用する方向で議論されています。
現在、年次有給休暇取得時の賃金の算定方式は、(1)平均賃金方式、(2)通常賃金方式、(3)標準報酬日額方式の3種類があり、企業はいずれかを選び、就業規則に定めることが義務付けられています。
-
(1)平均賃金方式:労基法第12条の平均賃金
-
(2)通常賃金方式:所定労働時間で支払われる通常の賃金
-
(3)標準報酬日額方式:健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する額
このうち平均賃金方式と標準報酬日額方式を採用した場合、月給制で働く労働者は月給から減額されない一方、日給制や時給制で働く労働者においては大きく減額されてしまう点が問題視されています。そこで、今回の報告書では通常賃金方式の原則化が提言されました。
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | 年次有給休暇取得時の賃金の算定方式は、平均賃金方式、通常賃金方式、標準報酬日額方式のいずれかを採用できる |
|---|---|
| 問題点 | 平均賃金方式や標準報酬日額方式で算定すると、日給制や時給制で働く労働者は不利益を被るリスクがある |
| 改正案 | 原則として、通常賃金方式で算定することとする |
なお、年次有給休暇の年5日付与の義務に変更はありません。
5. つながらない権利に関するガイドラインの策定
「つながらない権利」とは、労働時間外に業務上のメールや電話への応答を拒否できる権利を指します。労働者の心身の健康を維持し、ワークライフバランスを実現するために重要な権利ですが、現在日本では具体的な施策は講じられていません。一方、海外では法整備が進んでおり、中でもフランスは労働法により、つながらない権利が法制化されています。
そこで、今回の報告書では「勤務時間外にどのような連絡までが許容でき、どのようなものを拒否できるかといった社内ルールを労使で検討していくことが必要」として、ガイドラインの策定が提言されました。
日本労働組合総連合会が2023年に実施した「“つながらない権利”に関する調査2023」の回答結果を見みても、課題があるのは明らかであり、社内ルールの必要性は大きいといえます。
“つながらない権利”に関する調査2023の回答結果
- 勤務時間外に部下や同僚、上司から業務上の連絡がくることがある…72.4%
- 勤務時間外に取引先から業務上の連絡がくることがある…44.2%
- 勤務時間外に部下や同僚・上司から業務上の連絡がくるとストレスを感じる…62.2%
- 勤務時間外の部下や同僚・上司からの連絡を制限する必要があると感じる…66.7%
- 職場で実態把握のための調査等が行われたことがある…20.5%
- 勤務時間外の取引先からの業務上の連絡について職場のルールがある…19.9%
- ルールがあることで実際に取引先からの連絡が減った…73.3%
- つながらない権利によって勤務時間外の連絡を拒否できるのならそうしたい…72.6%
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | つながらない権利を守る具体的な施策は講じられていない |
|---|---|
| 問題点 | 勤務時間外や休日にも業務連絡が入り、労働者の休息確保が難しくなる恐れがある |
| 改正案 | つながらない権利の社内ルールの策定を推奨 |
6. 副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し
副業・兼業者の割増賃金の算定において、本業先と副業・兼業先の労働時間通算ルールを適用しない方向で検討されています。
労基法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされ、本業先と副業・兼業先の労働時間および割増賃金の算定は通算することと定められています。
上記に対し、副業・兼業者の健康管理のため労働時間の通算管理は必要であるものの、割増賃金に関する労働時間の通算管理においては、制度が複雑であることから企業側の負担が大きく、副業・兼業の許可および受入れの障壁となっている点が懸念されています。
こうした背景から、割増賃金の算定における労働時間に関しては、通算管理を適用しない方向で議論が進められています。ただし、廃止が提言されているのは割増賃金の支払いに関する通算管理のみです。
労働者の健康確保のための労働時間の通算管理は継続されるとともに、同一使用者の命令に基づき複数の事業場で労働する場合は、引き続き割増賃金算定時の労働時間の通算管理が妥当であると考えられています。
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | 本業先と副業・兼業先の労働時間と割増賃金の算定は通算管理が原則 |
|---|---|
| 問題点 | 企業側の負担が大きく、副業・兼業の許可や受入れの障壁になっている |
| 改正案 | 割増賃金の算定における労働時間に関しては通算管理を適用しない |
7. 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
法定労働時間週44時間の特例措置の撤廃も検討されています。これまで見てきたとおり、法定労働時間は週40時間が原則です。ただし、特定業種のうち労働者が常時10人未満の小規模事業場においては、法定労働時間を「週44時間」まで延長できる特例が認められています。
労働者数のカウントは企業単位ではなく事業場単位で行うため、ある特定の事業場(支店や営業所)の労働者が常時10人未満の場合は、この特例の適用を受けられます。
厚生労働省が2023年に実施した「労働時間制度等に関するアンケート調査」では、特例対象事業場の87.2%が特例を利用していないという結果が示されました。これを受け、特例措置はおおむね役割を終えたというのが労働基準関係法制研究会の見解です。改正後は法定労働時間週40時間への1本化が見込まれています。
ポイントは次のとおりです。
| 現行 | 一定の要件を満たす事業場では、法定労働時間週44時間の特例が認められている |
|---|---|
| 問題点 | 多くの事業場で特例が利用されていない |
| 改正案 | 法定労働時間週44時間の特例措置を廃止する |
キヤノンマーケティングジャパングループの
「人事労務アウトソーシング」は、人事労務の煩雑な課題を解決します。
どんな実務対応が必要になるのか?見落としがちな観点を整理

労基法の大改正は企業の実務に大きな影響を与えます。ここでは、人事労務担当者が着目すべき点をまとめました。
また、シフト勤務や変形労働時間制を採用している企業では、休日の特定義務化がシステム運用やシフト設計に直結するため、法定休日の定義と勤怠管理上の休日設定ルールを早期に確認しておく必要があります。
報告書では「現場運用に支障をきたさない範囲で、休日の明示化を進める」方向性が示されており、システム改修・就業規則改訂・労使協定の整合性を並行して検討することが求められます。
就業規則や雇用契約書の見直しが必要になる可能性
本記事で解説した「14日以上の連続勤務の禁止」「法定休日の特定」「勤務間インターバル制度の義務化」「有給休暇の通常賃金方式の採用」「副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの廃止」「法定労働時間週44時間の特例の廃止」において、就業規則や雇用契約書の変更が必要になる見通しです。
労基法では、就業規則が法令に反することを禁止しています。法改正後早急に対応できるよう、どの項目の変更が必要になるかをあらかじめ整理しておくと安心です。
勤怠・給与システム改修の検討も必要
休日や賃金に関する法改正であることから、勤怠システムや給与システムの改修も必要となります。システムベンダーと相談のうえ、早めに準備を進めていきましょう。勤怠・給与システムの中には、法改正の際に自動でシステムがアップデートされたり、時間外労働などを予測して法令準拠をサポートしてくれたりする商品もあります。
働き方が多様化する中、今後も法改正は継続的に行われるものと考えられます。今回の大改正を機に、法改正対応システムに切り替えるのもひとつの選択肢です。
従業員説明・教育体制の整備が求められる
労基法106条では就業規則の周知義務が定められています。主な周知方法として「事業所内への掲示」「書面の交付」「電子データによる公開」などが挙げられます。
しかし、たとえば「つながらない権利に関するガイドライン」など新しいルールの周知に関しては、直接の説明が必要なケースもあります。同時に、従業員の意識改革や教育も求められるでしょう。各部門の責任者等と連携し、どのように規則やルールを浸透させていくかを検討する必要があります。
グループ会社への展開やルール統一も重要な論点に
グループ会社や子会社、支店や営業所が複数ある場合でも、就業規則の作成・変更・届出は事業場単位で考えるのが原則です。ただ、テレワークやデジタルデバイスの普及に伴い、労働者が必ずしも事業場で働いているとは限らない現状を踏まえると、就業規則は事業場単位から企業単位で検討する必要性が生じてきます。
その場合、企業全体でルール統一化に向けた取り組みが必要になるうえ、細かな点では各事業場の実情を考慮した柔軟な判断が求められるようになります。法改正対応に向けたプロジェクトを立ち上げるなどして、各事業場の状況を把握できる環境をつくることが先決です。
滞りなく法改正に対応できるよう、余裕をもったスケジュールでプロジェクトを進めていきましょう。
実務対応に漏れがないか確認しよう|改正対応チェックリスト(無料DL可)

労基法改正に先立ち、企業の人事労務担当者が行うべき活動をチェックリストにまとめました。現時点(2025年8月)では議論の最中のため、具体的な取り決めを支援するものではありませんが、大枠の方針決めや実態把握にお役立ていただけるものと考えます。
詳しい対応方法や実務の整理に役立つ資料は、下記より無料でダウンロードいただけます。
“全部自社で対応できるか”を判断するために知っておくべきこと
改正労基法の施行までまだ時間はあるとはいえ、すべて自社で対応できるのか不安に感じる人事労務担当者もいるでしょう。法改正対応の方法には、自社で完結する方法のほかに、アウトソーシングの活用という選択肢があります。ここでは、内製対応のメリットと問題点、アウトソーシング活用の選択肢について解説します。
内製対応のメリットとその限界
内製対応のメリットは、自社の制度や風土に合った柔軟な対応がしやすい点にあります。また、法改正対応や就業規則にまつわるノウハウを蓄積できるため、知識の継承や人材育成の観点からもメリットは大きいといえるでしょう。
一方で日々の業務と兼任することから、人材確保が困難になることも想定されます。人的リソース不足の場合は、ミスや業務の遅延、それに伴う担当従業員の業務過多やストレスも加味しなければなりません。
法改正対応は人事労務部門にとって最大の山場ともいえる業務です。十分な人的リソースがない場合、内製対応に限界を感じる企業は少なくありません。
外注=丸投げではない。「一部委託でリスクを避ける」という選択肢も
内製対応が困難な場合に選択肢に含めたいのが、アウトソーシングの活用です。アウトソーシングというと、業務全般を外部に委託するイメージを持つ方もいるかもしれません。しかしそうではなく、一部の業務を委託する方法もあります。
たとえば法改正対応など、高度なコミュニケーションや臨機応変な対応が求められる業務(コア業務)は自社で行い、それ以外の定型業務(ノンコア業務)をアウトソースするなどの方法です。「手間を減らすため」ではなく、「対応ミスを防ぐため、パフォーマンスを上げるため」にアウトソーシングを導入するという考えにシフトすると、活用の利点が明確に見えてくることがあります。
まとめ|法改正は“コスト”ではなく“リスク対応と信頼構築”の好機

2026年の労基法の大改正について、企業が影響を受ける項目とその準備対応について解説しました。施行までに時間的猶予はあるものの、スムーズに法改正に対応し、法令遵守に備えるためには、今から就業規則や勤怠管理の見直し、従業員教育について検討を始めることが重要です。
また、法改正の有無にかかわらず、制度の整備や体制の見直しは、企業の持続可能性や従業員エンゲージメントの向上にもつながるテーマです。今回の大改正を、従業員との信頼関係を構築する良いタイミングととらえることが成功への近道といえます。
法改正対応を自社で完結するのが困難だと感じる場合は、外部のリソースをうまく組み合わせることも大切です。キヤノンマーケティングジャパンの「人事労務アウトソーシング」は、勤怠管理や給与計算などの定例業務から年末調整や住民税の更新、サポートセンターまでを包括し、人事労務の課題や負担を一気に解決する仕組みを整えています。人事労務業務でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
キヤノンマーケティングジャパングループの
「人事労務アウトソーシング」は、人事労務の煩雑な課題を解決します。
こちらの記事もおすすめです
「BPOソリューション」についてのご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BPO企画部







